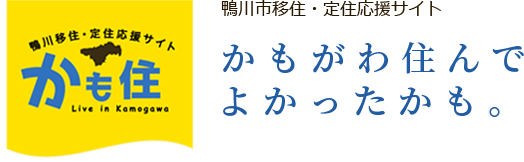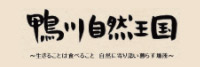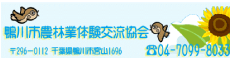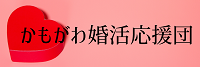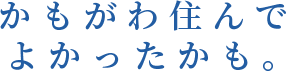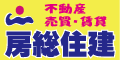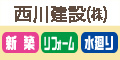本文
自家製のお灸で夏の疲れをいやそう!《ふるさと鴨川通信》

農業や田舎暮らしの知恵の学びを通じて、移住者や移住検討者の交流を図る「鴨川暮らしセミナー(かもくら)」。第12回のこの日は雲一つない秋晴れで、絶好の“農日和”となりました。

午前中、まずは座学からスタートしました。講師を務める刈込安義さんは、自らも農業を行いながら千葉県の職員として30年以上にわたって農業従事者を指導してきた“プロ中のプロ”。この日行う作業のポイントや、野菜ごとの注意点をていねいに解説していきます。
たとえばダイコンの間引き。「間引かない株を必ず手で押さえながら」「風が強いところでは根元に土寄せを」など、経験に裏打ちされたアドバイスは、本やネットだけではなかなか得られません。
ちなみに間引いたダイコンは「からし漬け」にするのが先生のお気に入りなのだとか。
座学の後は、かもくら畑で実習です。
カメムシの食害と闘い続けたエダマメもついに収穫。
こまめに「ストチュー(酢と焼酎、木酢液を混ぜ合わせた自然農薬)」を撒いたおかげか、実付きもなかなかです。
巨大な幼虫を発見!
座学で習ったポイントを活かして、カブやダイコンの間引き。作業の間も参加者同士、菜園談義で親睦を深めます。
害虫の食害が進んだ聖護院カブ。「もっと早いうちに対策しないと!」と刈込先生。害虫が増えないうちに、早めの農薬散布が必要でした・・・
この日種まきをしたのは、スナップエンドウ、キヌサヤインゲン、ミズナ、レタス、チヂミホウレンソウの5種。いずれも冬から春にかけて収穫できる野菜です。
野菜によって、畝に直播きしたり、トロ箱に播いたり、一度播いたものを広い場所に植えなおしたり・・・・・・農業は奥が深い! 先生と一緒に作業をすることで、体で覚えていきます。
昼食休憩をはさんで、午後は「田舎暮らしスキルアップチャレンジ企画」。鍼灸師で猟師の小野幸一さんを招いて、お灸づくりを教えていただきました。
まずは材料となるヨモギについての解説。里山であればどこにでも生えている植物ですが、よく似た毒草があるため注意が必要です。
次はセミナールームに戻って「もぐさ」づくり。収穫して乾燥させたヨモギをしっかり乾燥させ、石臼・すり鉢・フードプロセッサーなどでしっかりすりつぶします。
すり鉢はけっこう大変!
完成したもぐさ。
もぐさはすぐにお灸として使えます。紙筒に詰めて火をつけると、じんわり熱くなってきました。紙筒がないときは、濡らした和紙やスライスしたニンニクや生姜でも台座として代用できるそう。
続いて、小野さんから下半身の血行を促す「三陰交(さんいんこう)」や、肩こりやストレスに効くとされる「合谷(ごうこく)」など、いろいろなツボとお灸の効果を教えてもらいました。聞いたそばから、みんな次から次へとお灸に火をつけていきます。よっぽどお疲れのご様子?
気持ちがよくて簡単にできるお灸は、火の扱いとやけどにさえ注意すれば、自宅でのセルフケアにぴったりですね。
さて、次回のかもくらでは、ワケギの収穫やタマネギの植付、焼き芋などを予定しています。スキルアップチャレンジ企画では土壌改良に使える、「もみ殻くん炭」づくりにチャレンジする予定です。次回のかもくらもご期待ください!
参加者の感想
・今日は天気も良く、外作業も楽しくできました。これから育っていく野菜達が楽しみです。
・余った種の保存方法を学べたことは良かった。ムダがなくて良いですね。
・エダマメやエンドウの播種についてなど学べて良かったです。ヨモギやねこじゃらしがお茶になることにびっくりしました!!様々なツボがあり、その効能を知ることができ、今後も自分で試してみたいと思います。