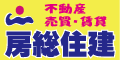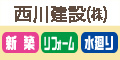本文
新型コロナワクチンの効果と副反応
このページは、ワクチンの効果と副反応をご案内するページです。
接種を受けることを迷っている方は、接種の効果と副反応のリスクの両方をご理解いただいた上で接種のご検討をお願いいたします。
なお、鴨川市の接種率は「ワクチンの接種率」をご覧ください。
ワクチンの効果
海外の研究では、新型コロナウイルスワクチンを接種した人の方が接種していない人よりも、新型コロナウイルス感染症(※)を発症した人が少ないことを示唆する効果が報告されています。
日本では現在、ファイザー社、武田/モデルナ社、およびアストラゼネカ社のワクチンが薬事承認されており、予防接種法における接種の対象となっています。
(※)新型コロナウイルスによる感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、症状が重くなると、呼吸困難等の肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。
さらに、ワクチン接種をしても新型コロナウイルスの感染をゼロにできるわけではありませんが、ワクチン接種後に新型コロナウイルスに感染した人は、ワクチン未接種で感染した人に比べて、
・排出する期間が短い
・無症候性感染者の割合が高い
・症状のある期間が短い
ということがわかっており、自身も重症化しにくく、周囲にも感染を広げにくいと考えられます。
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A <外部リンク>
mRNAワクチン(ファイザー社製・モデルナ社製)の効果
ウイルスのタンパク質をつくるもととなる情報の一部を注射します。それに対する抗体などができることで、ウイルスに対する免疫ができます。
いずれのワクチンも、薬事承認前に、海外で発症予防効果を確認するための臨床試験が実施されており、ファイザー社のワクチンでは約95%、武田/モデルナ社のワクチンでは約94%の発症予防効果が確認されています。
下記の表によると、性別では大きな違いはなく、また年齢別でも高齢者を含めいずれの年代も軒並み90%以上と極めて高い予防効果を示しています。
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A <外部リンク>
| 感染予防効果 | 発症予防効果 | |
|---|---|---|
| 男性 | 91% | 88% |
| 女性 | 93% | 96% |
| 16~39歳 | 94% | 99% |
| 40~69歳 | 90% | 90% |
| 70歳以上 | 95% | 98% |
| 基礎疾患なし | 91% | 93% |
| 基礎疾患1~2つ | 95% | 95% |
| 基礎疾患3つ以上 | 86% | 89% |
| 肥満 | 95% | 98% |
| 2型糖尿病 | 91% | 91% |
| 高血圧 | 93% | 95% |
ウイルスベクターワクチン(アストラゼネカ社製)の効果
アストラゼネカ社のワクチンは、ウイルスベクターワクチンであり、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質のアミノ酸配列をコードする遺伝子をサルアデノウイルス(風邪のウイルスであるアデノウイルスに、増殖できないよう処理が施されています。)に組み込んだワクチンです。このワクチンを接種し、遺伝子がヒトの細胞内に取り込まれると、この遺伝子をもとに細胞内でスパイクタンパク質が産生され、そのスパイクタンパク質に対する中和抗体産生および細胞性免疫応答が誘導されることで、新型コロナウイルスによる感染症の予防ができると考えられています。
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A
「mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンやウイルスベクターワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか。<外部リンク>」
副反応
コミナティ筋注添付文書・COVID-19ワクチンモデルナ筋注添付文書・バキスゼブリア筋注添付文書より
| 発現割合 | ファイザー社製 | 武田/モデルナ社製 | アストラゼネカ社製 |
|---|---|---|---|
| 50%以上 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛 | 接種部位の痛み、疲労、頭痛 |
| 10~50% | 筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ | 関節痛、悪寒、吐き気・嘔吐、リンパ節症、発熱、接種部位の腫れ、発赤・紅斑 | 倦怠感、悪寒、関節痛、吐き気、接種部位の熱感・かゆみ |
| 1~10% | 吐き気・嘔吐 | 接種後7日以降の接種部位の痛みや腫れ、紅斑 | 発熱、嘔吐、接種部位の腫れ・発赤・硬結、四肢痛、無力症 |
いずれのワクチンも
・接種直後よりも翌日に痛みを感じる方が多いです。
・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
・倦怠感や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が頻度が高くなる症状もあります。
・接種後すぐにアナフィラキシーや血管迷走神経反射が起こる可能性があります。
・mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンでは、ごく稀ですが心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。
副反応のリスクを十分理解し、ご自身の体調を整え、ワクチン接種をご検討ください。
アレルギー反応が心配されている、ポリエチレングリコール(PEG)やポリソルベートが含まれる医薬品について
他のワクチンや注射薬で、(重症でなくとも)すぐにアレルギー反応を起こしたことがある時は、新型コロナワクチンを接種すべきか、かかりつけの医師に相談してください。
日本で承認されているポリエチレングリコールを含むワクチンは、ファイザー社および武田/モデルナ社の新型コロナワクチンです。
ポリエチレングリコールとの交差反応性(予期した主反応以外の反応を開始する被物質の反応性)が心配されているポリソルベートを含んでいる既に承認されたワクチンは、アストラゼネカ社の新型コロナワクチンのほか、複数存在します。(※1)
(※1)沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー13)、インフルエンザHAワクチン「第一三共」、組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(ガーダシル)、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(エンセバック)、5価経口弱毒性ロタウイルスワクチン(ロタテック)、不活化ポリオワクチン(イモバックス)など(※2)
(※2)これまでこうしたポリエチレングリコールやポリソルベートを含む医薬品を使用してアレルギー反応が見られていない方については、引き続きこのような医薬品を使用することできます。
また、ポリエチレングリコールは大腸内視鏡検査時に下剤として使用する医薬品をはじめ、様々な医薬品に添加剤として含まれており、ポリソルベートも同様に複数の医薬品に含まれています。なお、ポリエチレングリコールは「マクロゴール」という名称で呼ばれることもあります。
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A コラム「アレルギー反応が心配されている、ポリエチレングリコール(PEG)やポリソルベートが含まれる医薬品にはどのようなものがありますか。<外部リンク>」
心筋炎・心膜炎について
mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン接種後、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎になったという報告がなされています。
特に、1回目よりも2回目のmRNAワクチン接種後に、高齢者よりも思春期や若年成人に、女性よりも男性に、より多くの事例が報告されています。
ワクチン接種後に、心筋炎や心膜炎を疑う事例が国内外で報告されていることについて、新型コロナウイルス感染症の発生状況も踏まえ、心筋炎・心膜炎の専門家は以下のような意見を示しています。
心筋炎・心膜炎の専門家の意見
●コロナ禍においては、心不全・不整脈・冠動脈疾患など心血管病の判断と管理が重要であり、若年者であっても胸部の症状(胸の痛みや違和感・息切れなど)があれば、精査や治療の継続が必要です。
●ワクチン接種後に心筋炎や心不全が疑われた報告の頻度やその重症度、突然死の報告よりも、新型コロナウイルスに感染した場合のそれらの発症頻度は高く、重症です。
●医学的見地から、新血管合併症の発症、重症化の予防および死亡率の減少を図るためにも、ワクチン接種は有効であると考えます。
●コロナ禍においても、ワクチン接種歴の有無に関わらず、突然死のリスクである血管病を早期発見するために、胸部の症状の出現など心血管疾患が疑われる時には、早くに近くのかかりつけ医などに相談し、必要に応じて精査や治療することが重要です。
心筋炎や心膜炎の典型的な症状としては、ワクチン接種4日程度の間に、胸の痛みや息切れが出ることが想定されます。特に若年の男性の方は、こうした症状が現れた場合には早くに医療機関を受診することをお勧めします。
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A コラム 「ワクチンを接種すると心筋炎や心膜炎になる人がいるというのは本当ですか。<外部リンク>」
血栓症について
アストラゼネカ社のワクチンでは、稀に珍しいタイプの血栓症が起きるという報告がありますが、適切な診断・治療方法も報告されています。なお、ファイザー社や武田/モデルナ社のmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンについては、現時点において、この血栓症の発症との因果関係は明らかととされていません。
●どのくらいの頻度で起こるのか
これまでの報告から、頻度にばらつきはありますが、極めて稀に起こるものであり、ワクチン接種約10万~25万回に1回程度といった報告があります。ワクチン接種1ヶ月以内に生じ、男性に比べて女性、特に若い女性の方が頻度が高いと報告されています。一般的に見られる下肢静脈等の血栓症と比べて頻度は稀と考えられていますが、注意深く情報収集が行われています。
●ファイザー社や武田/モデルナ社のワクチンでも起こるのですか。
ファイザー社のワクチンでは、接種後に同様の血栓症が起きたとして評価された事例がごく稀にあるものの、現時点においては、mRNAワクチンと、この血栓症の発症との因果関係は明らかとされていません。
●もし発症しても治療できるのでしょうか。
海外で発生した事例において、適切な判断や治療法に関する報告が増えてきました。一般的な血栓症とは治療薬などが異なることから、専門的な判断や治療が必要になります。このような血栓症が起きた際の治療法について、日本血栓止血学会、日本脳卒中学会の両学会において「血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療の手引き」を取りまとめられています。
●どんな血栓症なのですか
ヘパリンという薬を使った後に稀に生じる「ヘパリン原因性血小板減少症」と似ていることが報告されています。
これは、血小板第4因子とヘパリンの複合体に対して、抗体ができてしまうことで、血小板の減少とともに、様々な静脈や動脈に血栓ができてしまう病気です。
一般的な血栓症は、下肢の静脈等にできることが多いですが、アストラゼネカ社のワクチン接種後に生じた血栓症は、脳の静脈やお腹の中の静脈などにも生じ、脳静脈洞の血栓症を起こした方では、脳出血も同時に起きやすくなることが報告されています。このため、早期に診断して、適切な治療を行うことが重要となります。
●日本でもアストラゼネカ社のワクチンは接種されるのですか。
令和3年8月3日より、原則40歳以上の方(ただし、他の新型コロナワクチンに含まれる成分に対してアレルギーがあり接種できない等、特に必要がある場合は18歳以上の方)は接種が可能となりました。
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A 「ワクチン接種後に血栓症が起きると聞いたのですが大丈夫でしょうか。<外部リンク>」
新型コロナワクチン予防接種についての説明書(アストラゼネカ社ワクチン) [PDFファイル/1021KB]
アストラゼネカ社COVID-19ワクチン接種後の血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療の手引き [PDFファイル/781KB] (日本脳卒中学会、日本血栓止血学会)
接種日以降に副反応があらわれたとき
千葉県コロナワクチン副反応専門相談窓口
電話番号: 03-6412-9326
受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
※視覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方はファックスをご利用ください。ただし、ファックスによるご回答の場合、お時間をいただく場合があります。
ファックス番号(千葉県疾病対策課(:049-224-8910)
詳しくは、千葉県ホームページ「千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口について<外部リンク>」をご覧ください。
日本で接種可能なワクチンについて
2回目接種は、原則として、1回目と同一のワクチンを接種してください。
なお、鴨川市は、ファイザー社製のワクチンで接種を行っています。
| ファイザー社製ワクチン | 武田/モデルナ社製ワクチン | アストラゼネカ社製ワクチン | |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 12歳以上 | 12歳以上 | 40歳以上 |
| 接種間隔/回数 | 3週間の間隔で2回(※1) | 4週間の間隔で2回(※2) | 4~12週間の間隔で2回(※3) |
| 1回投与量 | 0.3ml | 0.5ml | 0.5ml |
| 用法 | 筋肉注射 | 筋肉注射 | 筋肉注射 |
| ワクチンの種類 | mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン | mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン | ウイルスベクターワクチン |
【接種間隔】
(※1)接種後3週間を超えた場合は、できるだけ早くに2回目の接種を受けてください。
(※2)接種後4週間を超えた場合は、できるだけ早くに2回目の接種を受けてください。
(※3)最大の効果を得るためには、8週以上の間隔を追いて接種することが望ましいとされています。8週以上あけて2回目の予約を取ることが難しい場合は4~12週間空けて、必ず2回目の予約をお取りください。また、接種後12週間を超えた場合は、できるだけ早くに2回目の接種を受けてください。
ファイザー社製ワクチン(コミナティ筋注)
コミナティを接種される方とそのご家族へ [PDFファイル/1.01MB]
コミナティ(ファイザー)接種を受けた後の注意点 [PDFファイル/645KB]
新型コロナワクチン予防接種についての説明書(ファイザー社ワクチン用 2021年9月) [PDFファイル/876KB]
12~15歳のお子様と保護者の方へ 新型コロナワクチン予防接種についての説明書(ファイザー社ワクチン用 2021年9月) [PDFファイル/958KB]
ワクチンの開発に当たって、国内外での臨床実験(治験)で接種後に生じた様々な事象(症状、疾病など)の件数や頻度は、薬事審査の歳に審査され、添付文書などに記載されています。
新型コロナワクチン「コミナティ筋注」(ファイザー株式会社)添付文書 [PDFファイル/905KB]
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンについて<外部リンク>
武田/モデルナ社製ワクチン(COVID-19 ワクチンモデルナ筋注)
COVID-19 ワクチンモデルナ筋注の接種を受ける方へ [PDFファイル/736KB]
COVID-19 ワクチンモデルナ(武田薬品)を接種した方へ 接種を受けた後の注意点 [PDFファイル/572KB]
新型コロナワクチン予防接種についての説明書(武田/モデルナ社ワクチン用 2021年9月) [PDFファイル/912KB]
12~15歳のお子様と保護者の方へ 新型コロナワクチン予防接種についての説明書(武田/モデルナ社ワクチン) 2021年9月) [PDFファイル/987KB]
ワクチンの開発に当たって、国内外での臨床実験(治験)で接種後に生じた様々な事象(症状、疾病など)の件数や頻度は、薬事審査の歳に審査され、添付文書などに記載されています。
新型コロナワクチン「COVID-19ワクチンモデルナ筋注」 添付文書 [PDFファイル/378KB]
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンについて<外部リンク>
アストラゼネカ社製ワクチン(バキスゼブリア筋注)
新型コロナウイルスワクチンバキスゼブリア筋注を接種される方とそのご家族へ [PDFファイル/2.88MB]
バキスゼブリア(アストラゼネカ社)を接種した方へ 接種を受けた後の注意点[PDFファイル/566KB]
新型コロナワクチン予防接種についての説明書(アストラゼネカ社ワクチン用 2021年9月) [PDFファイル/1021KB]
ワクチンの開発に当たって、国内外での臨床実験(治験)で接種後に生じた様々な事象(症状、疾病など)の件数や頻度は、薬事審査の歳に審査され、添付文書などに記載されています。
新型コロナワクチン「バキスゼブリア筋注」添付文書 [PDFファイル/397KB]
ワクチン接種を受けることができない方
・体温が37.5℃以上の方
・重い急性疾患にかかっている方
・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症の既往歴のある方
・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方
上記に加え、アストラゼネカ社のワクチンの場合は、以下の方も接種することができません。
・ワクチン接種後に血小板減少症を伴う静脈もしくは動脈の血栓症を起こしたことがある方
・毛細血管漏出症候群の既往歴のある方
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A 「ワクチンを接種することができないのはどのようなひとですか?<外部リンク>」
接種をするのに注意が必要な方
接種会場にて、医師の問診により接種を見合わせることがありますので、以下に該当する場合には接種前に医師に伝えてください。
また、接種に対して不安のある方は、事前にかかりつけ医にご相談してください。
・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た場合
・過去にけいれんを起こしたことがある方
・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
・抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方(新型コロナワクチンは筋肉内に注射することから、接種後の出血に注意が必要とされています。)
参考:厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A 「ワクチン接種に注意が必要なのはどのような人ですか?<外部リンク>」
すでに新型コロナウイルスに感染した方について
すでに新型コロナウイルスに感染された方もワクチン接種をすることができ、現時点では通常どおり2回接種します。
体調や治療内容等、総合的に主治医の判断を仰ぐことを基本とし、症状出現または無症状での検査陽性判明日から約4週間以上経過していることが望ましいとされています。
カシリビマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)等の抗体カクテル療法を受けた場合は、治療終了後から3ヶ月程度あけて接種することが勧められています。
詳しくは、以下の厚生労働省の資料、サイトをご覧ください。
既感染者への接種について(第21回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋) [PDFファイル/1.11MB]
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A 「新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか?<外部リンク>」
副反応による健康被害が起きた場合の補償について
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。