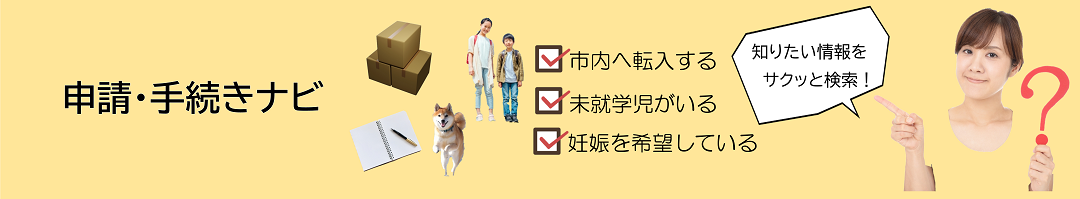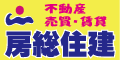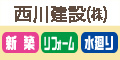本文
国民健康保険で受けられる給付
国民健康保険で次の給付が受けられます
医療の給付
病気やケガのとき、医療機関などの窓口にマイナ保険証等を提示すると、保険診療分の医療費は一部負担金を払うだけで済みます。(残りの費用を国民健康保険が負担します。)
70歳以上75歳未満の方には、高齢受給者証と資格確認書が一体化された「国民健康保険資格確認書兼高齢受給者証」が交付されます。(マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。)
療養費
緊急時や旅行先などでマイナ保険証等を提示しないで診療を受けたとき、コルセットなどの治療用補装具代がかかったときなど、いったん全額自己負担となりますが、申請をして審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払戻されます。
申請に必要なもの
療養費の種類・申請に必要なもの [PDFファイル/44KB]
高額療養費
月の1日から末日までにかかった医療費(保険適用分)の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が申請により、高額療養費として支給されます。
高額療養費の申請方法
診療月から最短で2か月後に世帯主に申請書を送付します。申請書が届いたら、申請してください。
・医療機関等から診療報酬明細書が月遅れで国民健康保険に届いた場合は、申請書の発送が遅れることもあります。
・申請期間は、原則、診療月の翌月の1日から2年間です。
申請に必要なもの
・国民健康保険高額療養費支給申請書(市から申請書を送付します)
・認印
・振込先(世帯主)の口座がわかるもの
(世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任状が必要です。)
・世帯主および申請書に書かれている人全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の自己負担限度額(月額) [PDFファイル/63KB]
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額 [PDFファイル/70KB]
限度額適用認定証
限度額適用認定証(非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を事前に取得することで、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したとき、「出産育児一時金」を支給します。
妊娠12週以上であれば、死産や流産でも支給されます。
申請に必要なもの
・マイナンバーカードまたは資格確認書
・母子手帳
・合意文書(直接支払制度を利用しないおよび保険者名が記載されているもの)
・出産費用の領収・明細書
・世帯主の口座がわかるもの
・認印
出産育児一時金の直接支払制度
直接支払制度とは、「出産育児一時金」が保険から分娩機関に直接支払われる制度です。このため、分娩機関の窓口で、「出産育児一時金」を超えた費用のみの支払いとなります。対応していない分娩機関もありますので、詳しくは、分娩機関にお問い合わせください。
出産にかかる費用が「出産育児一時金」を下回った場合、差額支給します。対象世帯には、申請書を送付します。
葬祭費
国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に「葬祭費」を支給します。
申請に必要なもの
・亡くなった方の資格確認書
・申請者(葬儀を行った方、喪主)が葬儀を行ったことのわかるもの (会葬礼状または葬儀の領収書)
・申請者の口座がわかるもの
・申請者の認印