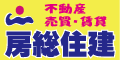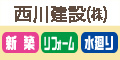ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
郷土資料館・文化財センターの常設展示
郷土資料館
1階展示室
農家のくらし
江戸時代から昭和時代前半までの農家のようすを再現しています。土間、居間、座敷のモデルと調度品を展示しています。
農具や漁具などの民俗資料


農具や漁具をはじめ、鴨川の地で使われてきた生活用具を展示しています。
2階展示室
武志伊八
郷土出身の彫物大工、武志伊八郎信由は、「関東に行ったら波を彫るな」という伝承があるほどの名人。通称「波の伊八」。「安房の三名工」の一人。
欄間彫刻2点を常設展示するとともに、数多く現存する作品を写真で紹介。大山寺不動堂向背の実物大写真もあります。
民俗資料

明治から大正にかけての教科書・お金の他、人力で動かす消防ポンプ、林業用の大きなノコギリ、機織り機などを展示しています。
郷土の偉人コーナー

郷土の生んだ政治家、元大蔵大臣、水田三喜男氏の遺品やコレクションや、鉈彫りの技法を用いた彫刻家、長谷川こう氏の彫刻作品、郷土出身のアララギ派の歌人、古泉千樫に関係する資料などを展示しています。
文化財センター
展示室
舟型石棺

大正15年、後広場1号墳で発見された古墳時代後期のくり抜式舟型石棺です。凝灰質砂岩製で千葉県唯一の資料です。石棺の内部には人骨1体と、金銅装大刀を含む7振の直刀、刀子、鉄鏃が副葬されていました。
七鈴獣形文鏡(複製)

嶺岡中央林道の造成時に発見された墳墓から見つかったものです。